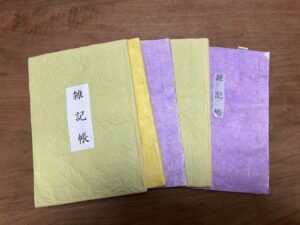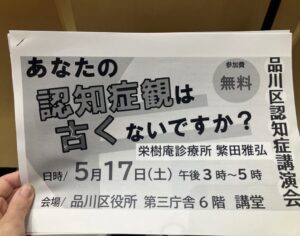時空を超えてー春男の雑記ー96 セリ市の中から
◆戦後の仲介業者は、仕入れの大半を市場に依ってなされていた。吾々駆け出し店員の仕事は毎日の様に市場に出かける事である。坂磯商店の売り手の間崎徳助さんは、今でも良い印象が残っている人である。一寸兎の様な親しみ深い人で随分お世話になった。
◆先ずこの人の心使いには敬服した。ちゃんと下見をして、手を出せば落として呉れるのだ。俗にいう新米だからと言ってかぶせたりはしなかった。後に田野の銘木市場に移って行かれたが、「アマッタ」と言う掛け声で調整し乍ら、遠路市場へ来てくれた夫々の店の人達に気を配り、品物を公平に分配していた。要するにみやげをこしらえて呉れていたのである。
◆たまたま骨董屋の古本に市売りの様子が出ていたのを読んだので書いて見たい。東京広尾の古美術商山﨑さんは、昭和7年芝の「松留」へ奉公に出たのだが「松留」の主人は、客を相手に頭を下げる商売よりも、戦場に臨む意気で、業者を相手の商売に力を注ぐ典型的な古いタイプの骨董屋であったから、自然と山崎さんも古い型の骨董屋としての人生を歩んだ。
◆セリ売りの振り手として山崎さんの捌きは実に綺麗なものであった。彼は市を盛り上げようと思ったら、初めの二、三十点は損を覚悟し、二束三文で売りさえすれば良いと言う。安い処の声で次々に決めて行くと、市が熱気に溢れ、今日は息つく暇も無いぞと書い手は総立ちになり、欲しい物を買い損ねてはならじと次第に熱が入り、いきなり高い値がつくと、負けるものかと更に高値を追う。終わって見ると、売りが綺麗だと、収支決算は上がっている
ものだと言う。「今の半分素人の様な業者は、未練がましくいつまでも少しでも高く売ろうと引っ張りやがってみっとも無いったらありゃ
しない」と手厳しい。(骨董屋という仕事・青柳恵介著より)
◆次に「古書肆の思い出・反町茂雄著」より。矢張り昭和初期の古本市売り風景を拾い出して見る。『連合会(東京)は当時日本一のセリ
市であったろう。セリ手は眼前に置き並べられた古本の中から手早く一冊を抜いて胸の辺りまで上げるとトタンに「青山の債権」と高く
句口早に言う。間髪入れず「二円五十」と六七人の声が飛ぶ。早い声に落ちるのだが、誰のどの声か分からない。五分の一秒か八分の一秒の遅速であろう。振り手はすぐに「二円五十!三光屋さん」と判定する』。振り手は一瞬の遅速と声で落札者の判定をするのだから之も
すすごいものだ。
◆因みに著者の反町と言う人は東大卒業後、神田の一誠堂へ奉公した。特筆すべきは、ここで天理教に中山管長と出会うのだが、あの有名
な天理図書館の善本は、二人の商売を抜きにした交流から生ずるのである。二人は酒を一滴も飲まなかったと言う。その後、反町氏は
カカタログ販売をするのだが、正しく今のホームページの始まりで、昔の入札品書の様な保存書のカタログであった。
(平成12年7月5日)