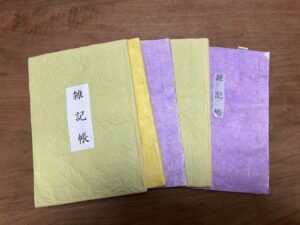時空を超えて−春男の雑記−89 老舗のこだわり
◆心斎橋北詰を一二軒入った東側に、昔から駸々堂書店があった。1933年の創立だから私達子供の時分からあったのだが昨年末からシャッターが降りたままになっていると思ったら、間もなく倒産し、旧店舗は、薬屋に変わってしまった。蛍光塗料のグリーンの品書きに、赤い字の値段・・・・、顔をそむきたくなる現代スーパー商法の安売店になっていた。
◆1936年に出来た大阪そごうも撤退の様子である。そごうは御堂筋を渡ったアメリカ村に群がる若者をどうして取り込めなかったのかと、近年のアメリカ村の発展に思いを致す時、大阪そごうが経営難に追い込まれる迄、無為に過ごした年月が惜しまれる。一方アメリカ村で商売をしている人達の、栄枯盛衰も又目まぐるしいと聞いている。そして成功した人はブランド品の販売を目指して、横堀筋へ或いは堀江と移って行く。そして燎原の火の如く意外に早いのである。
◆2月25日の朝日新聞の長針短針に井野瀬氏が「老舗の味、活路を開くのはこだわりか」と言う一文を載せている。イギリスの事で、今の日本に通用するかどうか分からないが、良いなあと思うので触れてみたい。
◆昨年、「ダックス」で知られているシンプソンが閉鎖に追い込まれた。地下一階地上六階のゆったりした建物で、紳士はそこで装いを調え、地下にある寿司バーで腹を満たし、二階のコーヒーギャラリーで、ひと時を楽しむのである。だから皆そのビルの行末を見守っていた。そして昨年秋その変身振りに驚いた。なんとその建物が、ヨーロッパ最大の規模の書店に大変身したのである。
◆一歩店内に入れば、コーヒーを啜りながら新聞や雑誌を読み、インターネットで本を探し、疲れたら食事をし、気に入った本があれば一杯飲みながらページをめくる・・・。丸一日楽しめる空間である。建物にはシンプソン時代のオリジナル、大理石の階段や、その美しいライオン等がそのまま活かされている。ここにあるのはモノの消費ではなく、時間の使い方へのこだわりだ。店が無くなってもこだわりは受け継がれる。これが老舗かも知れない。
◆日本的なこだわりと言う点では、本でしか知らないが、京都の旅館俵屋等は見事なものである。京都南座の前の五十六屋の五色豆、鬼広永のはくせんこう、それらは店頭売りしかしないが、こじんまりと老舗を守っている。そこでは続けていく事がお客さんに対する最大のサービスであると言う発想の様だ。
◆私は大の甘党だが先日来有名な売出し中のお饅頭を続けて頂いた。その後ふと気が付いた。何か変なのだ。オートメーションの饅頭には手のひらで握る職人のこだわりと老舗のこだわりがないのである。それが微妙に饅頭の味に影響している様に思われてならない。
(平成12年3月20日)