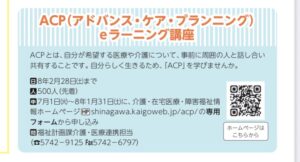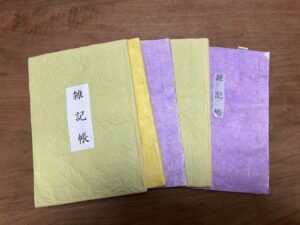時空を超えてー春男の雑記ー102 ものづくりの話(下)
◆ある書店の二階の文庫本の売り場で小泉八雲の「怪談」が欲しいと言ったら、そんな人知りませんなあと言うのである。明治時代、イギリスより来日した小説家であり、文芸評論家であり、東大早稲田で英文学の教授までしたかなり有名な人なのに、店員二人が顔を見合わせて知りませんなときたらいささか愕然とする。月日の流れにどんどん忘れられ、切り捨てられていくのだ。
◆私達の一番恐れているのは技術の切り捨てである。大工さんは、一日、鋸と金槌と釘、それにボンドがあれば仕事が出来るのである。組み物の仕事がどんどん現場から無くなっていくと言うしかないのだ。鋳物等の汚れ仕事は、ほとんど海外へ行った様で、東京の町工場では金型の流失を食い止める為の新しいITに依る技術開発に成功したのをラジオで放送していた。
◆話として一般に知られている技術伝承の方法として国家事業で行われているのは、二十年に一度遷宮と言う型をもって社殿を初めとして備品、宝物まで一切を造り直しているお伊勢さんである。また、ハイテクの先端を競うカメラの業界でも、時計の業界でも技術を温存する為に莫大な投資をしている様だ。
◆先日の朝日新聞にはカメラの日本光学「ニコン」の事が出ていた。そこには「匠の技」を前面に出し、ハイテク作業に依り、年々失われていく技術の温存が巧みに行われている様だ。ハイテク機器に飽きた消費者の心理を上手く引きずり出して商売にしている。復刻や復古調で、過去にヒットしたニコン「N3」を引っ張り出しておまけに予約限定商品として売り出し、予約満杯で納入期限を遅らしている。
◆勿論、メーカーにもそれなりの苦労はある様だ。何しろ四十二年ぶりの復刻であるから、先ず熟練工十二人を選んで半年間試作に、全工程の習熟に励んで、全体をマスターしてから製造に入ったと言う。実際の作業は分業にするが、最新のカメラと違って全工程を理解した上で職人的な勘を働かさないと性能は安定しないと言う。まだそこで、「S3」の製造に関わった元社員から手造りの秘伝を受け継いだのである。因みにニコンの現在の最高級品「F5」は三十六万二千円で、手造りの「S3」は四十八万円と言うのだから、ここらの処は読者諸賢のご見識に従うしかない様だ。
◆「S3」は一眼レフが普及する前、高級カメラの主流だった「レンズファインダー」方式で、ピントも絞りもシャッタースピードも全部手動である。となると、より便利で、ワンタッチですべてOKという商品が多い今日、この高級カメラを買う人は何を求めているのだろうか。
◆ここで旋盤工であり、作家である小関智弘さんは「道具とは、本来人の使うものだ。現在のデジタル化した機械は人が関与する余地がない装置になっている。復刻商品は道具を持ちたいと言う消費者の欲求に答えたものだ。」と。・・・・成る程言えている。
(平成12年10月5日)