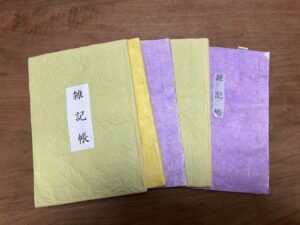時空を超えてー春男の雑記ー104 お伊勢まいり
◆「いせまいり、大神宮へも一寸より」なんて言う江戸川柳があるが、伊勢参りも初めからこんな結構なものでは無かった様だ。大体日本人は昔から旅が大好きで、万葉集に集められた歌四千五百首のうち、旅に関するものは千二百首在ると言う。もともとお伊勢さんは、天照大神を祀る天皇家の氏神であったので、一般庶民とは関係が無かったのだが、平安時代が過ぎる頃より天皇家の力がだんだん弱ってきたので、お伊勢さんも自立を考えざるを得なくなった。そこで神宮に所属する御師を使って日本国中へお札を配らすのである。
◆秋ともなると、自分の領分の随分と山の中の家へも皇大神宮と書いたお札を配り、お初穂料を貰うとそのお返しに伊勢暦を渡していた。この暦を見て百姓は、種まきの時期を知り、漁師は汐の満潮干潮を知るのである。こう言う御師階級の人達の地味な努力が後に、お伊勢参りのブームを呼び起こすのである。
◆暦年で六百万人、御蔭参りなどの年は七百万人を超えたという。今に残る旅日記等から面白そうな処を引いて見る。昔は庶民にそうそう余分な金のある筈は無く、知恵者の御師が知恵を絞り、講を造って代表制度をこしらえた。部落、町内で、それぞれが講の月掛けをし、籤に当たった数人がその年の伊勢代参をする事になる。その講には次の様ないくつかの決まりがあった。(一)、一日の行程は十里(約四十キロ)とする。(二)、病人が出た時は治るまで待ってやる。(三)、足を痛めた者があれば、馬や駕籠に乗せ費用の半分は外の者が負担してやる。(四)、出家、女子と道づれにならない・・・等だ。
◆伊勢に着けば、あとは御師が全部面倒を見てくれ、宿泊、見物、お参り大神楽納め等、至れり尽せりの今の旅行社以上のサービスをする。お参りをすました人々は古市の町でゆっくり旅の疲れを癒して、松坂木綿の反物などを買い込んで家路につく。だがここでせんど遊びほうけて帰って来た男達の話を聞かされる一方の女房や子供は面白くない。そこで起こるのが、エヤナイカ、エヤナイカの掛け声の御蔭参りである。伊勢音頭の文句の「伊勢に行きたや 伊勢路は見たい せめて一生に一度でも」てな事になる。宇治の茶摘女の中から、又徳島の寺子屋の子供達の中からそう言う声が上がると人々は皆着のみ着のままでお伊勢参りへと旅立つのだ。その数は三ヶ月で三百万人と言われた。
◆熱狂する人達に、沿道の物持ち達は騒ぎの沈静する何ヶ月間は、お粥を炊き出し、草鞋に手拭い銭まで渡し、宿も提供した。その為大変無秩序な集団行動なのに暴動略奪は一度も起きなかった。
「何人のおわしますかは知らねどもかたじけなさに 涙流るる」と西行法師は詠んだが、初めの句とは大分距離があるが、伊勢さんも食べて行かねばならない・・・。
(平成12年11月20日)