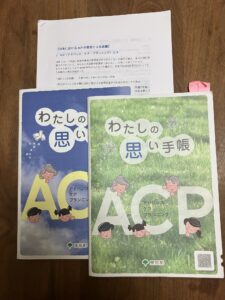時空を超えてー春男の雑記ー106 年の瀬
◆「年の瀬や 年の瀬や 水の流れと人の身は 止めて止まらぬ 色の道 浮世の義理の捨て処 頭巾羽織も ぬぎすてて 肌さえ寒き 竹売りの明日待たるる 宝船」
このさっぱり訳の分からないのは、昔の小唄の文句で、題は「年の瀬」赤穂浪士の一人大高源吾は、子葉と号する俳人であった。吉良邸討ち入りを明日に控えた師走の十三日、折しも事始めの大掃除に使う竹売りに身をやつし両国橋を渡った処で師匠の宝井其角に出会うのだ。そして「年の瀬や 水の流れと人の身も」と呼びかけられると子葉こと大高源吾は「明日待たるるこの宝船」とつなぐ。と言う有名な話ではあるが、、、。
◆何も知らない其角は、弟子の子葉が余りにもみすぼらしい姿なので羽織を与えて別れたが、その帰り道、松浦候の隠居に会いこの話をすると流石に松浦候は武士、討入りの近い事をしり、其角に口止めをする。たまたまその夜、吉良邸の隣の本多家に泊まり込む様になった其角はその夜更け討入りを知るのだが、本多家へ挨拶に来たのが大高源吾だと言う良く出来た話である。
◆十二月も十五日を過ぎると一気に大晦日へと突き進む。元禄時代、江戸で長屋暮らしをしている庶民の大晦日の風景を井原西鶴は「世間胸算用」で書いている。「暦という物は誠に正確なもので、年の初めの日があり、だんだん月日が経って否応なしに大晦日になる。こんな分かり切った事を皆何故平素いい加減な暮らしをしていて大晦日になって右往左往するのか」と言うのが言い分だが、長屋の住人達は幸か不幸か誰も掛売りしてくれず、オール現金なのだ。月末には家賃を払うのが日々の一寸した所帯の入用品、又は米味噌、薪、酢醤油、塩、油まで誰も掛売りしてくれないから、総て現金でその日その日を暮らすので節季節季の支払時分にも誰も集金等には来ない。誰を恐れて詫び言をする訳でも無く、古人の言う「楽しみは貧乏暮らしの中にある」を絵に描いた様な暮らしをしているのだ。
◆だが正月だけは一寸事情が違う。つまり三日間仕事に行かないので銭が入らぬのに、子供に着物の一枚でもと思うと若干の金が要るという事だ。そこで出番となるのが質屋で、入質の品物と借りた金を並べると①古傘一本、糸繰車一、茶釜一で銀一匁。②女房の常にしている帯、亭主の木綿頭巾、蓋なしの小重箱一組 茶升ニケ、七つ半の筬一丁、皿五枚、他二十三点で一匁六分。③大道芸人は、正月は大黒舞に変るので平素の分で三匁七分借りて充分な正月を過ごしている。物価も安かったのだろうが今の一、二万円である。面白いのはこれから品物は、どう見ても役に立ちそうも無いものだが、貸す方も借りる方も大真面目で、入用の金の借り貸しが行われていた事である。そして正月が過ぎるとそれらをぼちぼち受け出して、つまり金を返して又来年に備えたという事で、要は庶民の知恵なのだ。何時の時代も底辺たくましい様である。
(平成12年12月20日)