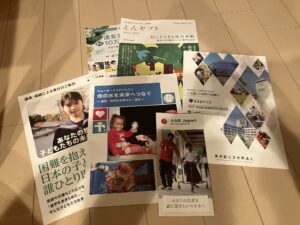時空を超えてー春男の雑記ー113 四天王寺の七不思議
◆千四百年も前に出来て未だにその伝統を伝える四天王寺には、それはそれなりにいろんな言い伝えがある。大衆の寺として市民の中で生きてきた寺、又市民の崇拝を受けてきた寺にはそれなりの伝承があって当然である万治二年と言うから今から三百五十年前、徳川中期に市川喜雲という人がそれらを集めて「京童跡追」と言う冊子に書いているのから抜き出してみる。
◆(一)五重塔の九輪の支えは閻浮壇金一千両で鋳造しているので永遠に金色は変わらない。之は仏教の世界で、お釈迦様の修行した須弥山の南の島で採れる最高級の砂金なので之を大量に使った九輪の金色は永遠の光を放つだろう。またこの九輪の金色は仏法の盛衰に依り替わって行くとも言われ、四天王の縁起には聖徳太子自らがこの九輪を造られたと言い伝えている。
(二)亀井の井戸は、天竺、龍宮、四天王寺と流れてきているので枯れる事はない。これは気宇壮大な話であって、奈良二月堂のお水取りの閼迦の水は若狭から流れて来るというのとはけたが違う様だ。
(三)金堂の雨落には天竺の銀が敷かれているから窪まない。お釈迦様が説法された天竺の霊鷲山の銀を龍が運んで敷き詰めたと言うのだ。之は聖徳太子が書かれた御手印縁起の中で「この地には七宝を敷けり」と云うとこから来ているのではないかと思われる。
◆(四)四天王寺の蛙は、池の底に住む十丈の大蛇を恐れて鳴かない。聖徳太子は「この地の中に池あり荒陵の池と名付くその奥深くして青龍つねに居処せり」と書いておられるのから出ていると思われる。
(五)金堂の柱は天竺の赤栴檀の木で造られているから永久に朽ちない。この場合赤栴檀は商売柄紫檀ではないかと思われる。
(六)中門の仁王は、仁王像王が造ったもので、門の上は鳥さえ飛ばない。
(七)境内の木は、金堂、五重塔より大きくならない若し大きくなっても枝は下を向く。
◆以上の様に四天王寺の境内には七宝を埋めた上に天竺からきた用材で永遠を念じて造営された此処では聖徳太子の威徳を恐れて蛙は鳴かず、仁王さんを恐れて鳥もその上を飛ばない、又木々も金堂、五重塔以上には大きくならないと言うのだから聖徳太子のご威光たるや推して知るべしだ。一説に四天王寺の雀は両足を一緒にピョンピョンと歩かず、鳩の様に行儀良く足を交互に歩くと言う。何しろ、聖徳太子ビイキ、天王寺ビイキの市民達は、何でもすべて良しと、その大きな懐の中に抱き込まれて信仰していたのだ。昔は随分人々の心も純真で良かった様です。
(平成13年4月5日)