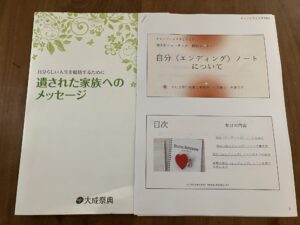時空を超えてー春男の雑記ー114 平家物語の人達
◆昨年松竹座で玉三郎の「壇浦兜軍記阿古屋の琴責」をやっていた。玉三郎はこの芝居で琴、三味線、胡弓を弾くのだが、それは稽古さえすれば出来るのだが、ままにならない一番心配なのはポイと出された夫々の楽器の調弦が狂わないかと言う事だと言っていた。楽屋、廊下、舞台の袖、舞台と全く温度が違うのである。風が通って涼しいのは舞台の袖で、一番暑いのは舞台の上である。役者が汗だくで熱演していると言う様に見えるが実はあそこは猛烈に暑い処である。大体琴の糸は絹糸で出来ていて、基本的には演奏会に出る度に張り替えるのである。新しい糸は延びるところへ持ってきて暑いからたまったものではない。一寸でも延びると音が下がるので、玉三郎はそれを大変苦にしていて、いくら考えてもどうにもならないので運を天に任して余り考えない様にしていると言う裏話をしていた。
◆舟の舳の竿の上に取り付けた扇を射落とせと命じられた那須の与一は、黒い太くたくましい馬に定紋を打った鞍を置いて汀へ乗り入れた。舟の舳に立つ官女は柳の五衣、要は黄緑の品の良い打ち掛けである。与一は紺の直垂に萌葱縅の鎧着て足白の太刀を佩き、兜はぬいで高紐にかけて颯爽と現れるのである。この場合、扇との距離は七段と言うから、一段六間としたら四十二間、三十三間堂の通し矢より大分遠く、やはり与一は名手である。それに年は十七才と言うから立派なものだ。
◆只、見事扇を射落として面目をほどこしたのは良かったが、平家方では二番煎じに老武者が又舟で出て来て舞を舞った。伊勢の三郎から、あれも射て仕舞えと命じられた与一はこれも射たので、老武者は舟底へ転がり落ちてしまった。平家方は一遍に白け、見ている内に舟を浜へ着け、三人の武者が降り立ち、「判官出て来て勝負せよ」と迫った。
◆世の中、人生にはつくかつかないがあると思うが、ここで判官義経の命を受けて、そんな者蹴散らしましょうと出て行った三保谷十郎はついていなかった。先ず馬を屏風が倒れる位見事に射られた。そこではと太刀をぬいて立ち向かうがそれもへし折られて長刀を持った武者に取り掛かられるこれは叶わじと逃げると兜の錣をむんずと掴まれ力比べとなり、やっと振り切ってのがれたが、その時錣が千切れたと言うからどちらも大力であるそれもその筈、長刀の使い手は、平家随一の勇者上総の悪七兵衛景清であった。この景清が先に出てきた阿古屋の情夫である。景清は徹底的に頼朝を狙っていたので、景清の女ってである阿古屋をつかまえて景清の行方を探ると言うのが芝居の筋である。
◆此処で今一人すごい女を書きたい。木曽義仲の乳兄弟今井兼平の妹巴である。義仲について最後の栗津野まで来て義仲に去るように言われる。ならば巴最後の手柄にと敵方三十騎程の中へ一人突っ込むや、東国でも豪の者と聞こえた恩田八郎と言う大力の剛の者におし並び、むんずと組んで引き落とし、吾が乗りける鞍の前輪に押し付けて、ちっとも動かせず首ねじ切って捨てにけり・・・とある。今も昔も女は強いですね。ああこわやの・・・。