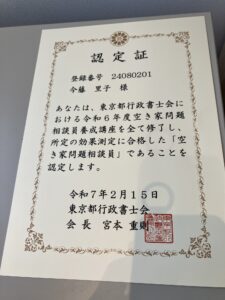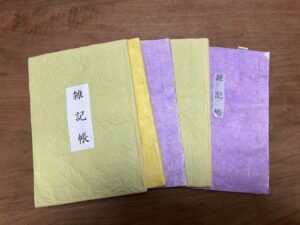時空を超えてー春男の雑記ー88 立川文庫
◆周防町通りを真っ直ぐ東へ行き、松屋町を過ぎると間もなく上町台地の坂にさしかかる。通称楠坂である。
坂の頂上と思われる谷町六丁目位の所で道の真中を楠の老木がふさいでいる。鋸を入れると血色のおが屑が出てくるので、木挽きは怖がって手を付けないと言う。根本に巳さんの嗣がある。ここをもう少し東へ下がった右側に真田山公園がある。
◆大阪冬の陣に、大阪城南の天王寺口を守った真田幸村は、真田丸と言う砦を構築した。その名残が真田山公園として残って居り、嬉しい事に大阪城に通ずる抜け穴が現存している。今なら考古学だが、その頃我々子供には大変身近な歴史遺産であった。然しよく考えると、大阪城に通じる抜け穴なれば北の方へ向いておらねばならないのに、この穴は南の方へ通っていた。
◆その頃の子供の読み物で一番は少年倶楽部であった。山中峰太郎の「敵中横断三百里」なんて実在人物の建川美次中将の実話なるものが出ていた。他に佐藤紅緑の「鳴呼玉杯に花受けて」等は素晴らしかった。紅緑はサトウハチロウ・佐藤愛子の親父さんである。少年倶楽部は五十銭で一銭や二銭の小遣いを貰っている我々の手には負えず正月のお年玉でしか買えなかった。
大抵は古本屋で月遅れを買ってきて読んでいた。そんな時、安くて面白い本が出てきたのだ。俗に言う立川文庫である。
◆この本で大活躍するのは真田十勇士で、その筆頭は甲賀流忍術の達人猿飛佐助、伊賀流霧隠才蔵なんて言うスーパーマンと、三好青海入道と言う力持ちの暴れん坊が三十六貫の鉄の棒をおがらの様に振り回し、群がる的をバッタバッタとなぎ倒す
ストーリーで血沸き肉躍るのだった。その歴史的事実と真田の穴は繋がるのだから真田山公園はよく行った。二三人の悪ガキ
が誘い合って穴の前でジッと立ち尽くして得心したような顔をして帰ってくるのである。
◆昭和十二三年、ひたひたと戦争の足音が押し寄せて来る頃、小学生の遠足でも近鉄の若江岩田にある木村長門守重成の墓や飯盛山にある楠正行の戦跡を尋ねたりした。これらは行けば本当に何も無い処なのだが、行くまでに先生がしてくれる夫々の歴史的事実の説明が結構楽しかった、そして国自体が満州事変、支那事変に備えて、臨戦体制に入って行ったのだ。
◆大阪城の豊国神社で、何かあると手伝っている女性がいる。この人は何時も手首に数珠を巻いている。お客さまなのに何故
と聞いてみると「大阪城内には元和の戦で死んだ霊魂が浮かばれる事なく彷徨っていて、私の様な霊感のある人間には寄って
くるのだ」と言っていたが、先日のラジオでも、南方に慰霊に行くとジャングルの薄暗い処で日本の兵隊が立っているのを見た
と言う土地の人が何人かいるそうだと言っていた。我々平和ボケをしているが、未だ遣り残した事が沢山あるように思えてならない。
(平成12年3月5日)