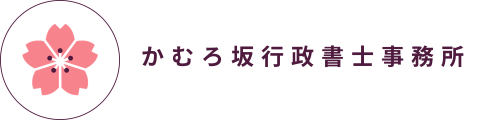時空を超えてー木々高太郎の雑記ー⑪諏訪の神
◆大和朝廷との闘いに破れた建御名方の神(大国主命の子供)は遠く信濃の国諏訪へと落ち延びて行ったのである。そこで自然との厳しい斗いの中で地方の豪族としての地歩を固めていく。この諏訪の地は、神懸り的な伝承と、人間臭さとの世界である。
◆秋が深まり、山々の草や木が樺色になると、夕方から夜にかけて小雪まじりの風が吹く。そして夜が明けると、一面の雪である。寒さも愈々厳しくなると、諏訪湖は毎日雷鳴の様なうねり声を上げる。数日の内に湖の上に御神渡(おみわたり)が出来る。一米程の氷の盛り上がりの道が、南の上社から北の下社の浜まで続くのだ。上社の男神が下社の女神の元まで逢いに行くのである。
◆曽良(芭蕉の高弟)は何度か諏訪で正月を暮らしている。この大変雪深い田舎の暮らしをえがき出した俳文がある。
◆年が改まり春だと言うのに、諏訪の山々に霞も立たないし、谷川の水もぬるまない。勿論、梅の花も咲かないし、鳥も春を歌わない。閉じ込められた山国の厳しい寒さは格別である。然し正月と言っても、この山国では堅苦しく麻上下に威儀を正す必要もないし、唯暖い楽なふうをして暮らすのである。
◆正月のことでもあるので伊勢暦を取り出して、春の野良仕事の段取りをしたり、一文銭を十枚二十枚と取り出して、松葉で何枚かづつくくり付けて杉原紙に包む事もなく子供の年玉にするのである。
◆信濃の古い正月風景を曽良は”袂より 春は出たり 松葉銭”と詠んでいる。元々曽良は御師の様な神職を職業としていた。元禄時代の事でもあり、風俗が華美に流れるのに反し、すたれ行く神道に関心が深かった様で、紀行文の中でも延喜式年に載っている様な神社を丹念に廻ったようだ。
◆御師は夫々自分の得意先の農家を伊勢神宮の御礼と、伊勢暦を持って廻るのである。
◆昔から日本は言霊の国と云う。そして神様にお願いする言葉が祝詞である。生神様を最大限に稱えるのだ。そして”私達はこの様な御供をして神様にお願い申し上げます。どうぞお聞き届け下さい”と御師が神と農民の仲立として祝詞を奏上する。言霊の国日本の神は、この御師の言葉を必ず聞いて呉れたのである。故に人々は神を崇め、信じたのである。日本にはこうした古き良い風習と時代があった。
(平成9年2月5日)