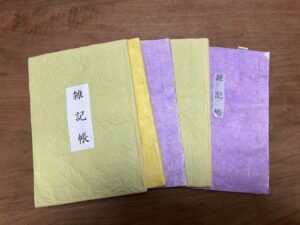時空を超えてー木々高太郎の雑記ー㉘ひぐらし
◆ここ高野山の一の橋から奥の院への参道は、四時を過ぎるとカナカナと蜩(ひぐらし)が鳴く。高い杉木立の下の石畳の路は、この八月の初旬、大阪では考えられない涼しい風が吹く。
◆お寺も大変である。これが売り物であろう白いペンキを塗った立札に徳川家墓所、芸州浅野家墓所なんて書いてある。熊谷直実さんと平の敦盛さんが並んでいて、それより古いといえば曽我兄弟が近くにおいでになる。今一つ解らないのは平安時代の道長さんや、紫式部女史の墓は何故ないのだろうか。
◆其の頃は、熊野権現の方が流行だったのだろうか。中の橋の手前右側に明智光秀さんと石田三成さんのが御近所同士にある。光秀の墓に付いて云うならば、滅ぼした秀吉も、云いかえれば光秀が悪者になってくれたから天下を取れた様なもので別に恨みつらみはないだろうが、三成となれば話が違ってくる。
◆天下を取った徳川家康さんにすれば、随分ジャマをしたイマイマしい奴であったに違いない。都の”市中引廻しのうえ打首”と言う普通なら何処かから文句の出そうな仕返しをしている。
◆私が問題にしているのは、この墓が誰が建てたのかと言う事である。幕府からにらまれたなら御仕舞だのにと思う。因に墓の台石には大正18年と刻んである。天正18年は秀吉が小田原城の北条氏を潰した年である。こうなると益々わからない。何しろ昔のことである。
◆墓石の一番大きいのは駿河大納言徳川忠長公が母の為に建てた物で、高さ十米だから貫禄がある。然しこの人も英邁である故に、兄家光に殺されるのである。
◆高野山の総本山は金剛峯寺である。太閤秀吉に子供が出来ると、養子の関白秀次は、身の危険を感じて僅かな供人と高野山へ逃げ込むのであるが切腹させられてしまう。本堂左奥の西の間、柳のふすま絵がある「柳の間」が秀次切腹の場所となった。高野山総本山本坊の正面のこんな場所が処刑の場と云う事はどうしてもわからない。秀次の関白と云う位に対するおもねりか、又太閤に対しての何かの思惑があったのだろうか。
◆あの壇ノ浦から逃げ出した平維盛も、高野山へ辿り着く。ここに親しい瀧口入道がいたので出家するのだが、ここはかくまってくれないと知ると熊野へ逃がれ、瀧口入道に見守られ熊野の海へと入水するのである。彼が案じ続けていた子供の六代は六波羅の探題に殺されてしまう。
◆高野山へ行けば救われると信じて来た人が皆救われていない。これは一体どうしたことであろうか。年々歳々この聖地に杖を引く人が百万を超えると云う。現世を逃れ救いを求めて・・・。
(平成9年8月25日)