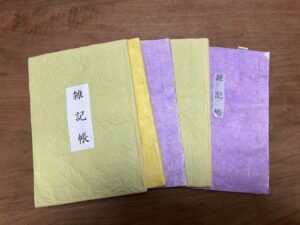時空を超えてー木々高太郎の雑記ー㉙三月もたてば霙(みぞれ)が降る
◆冷夏だ冷夏だと騒いでおきながら、盆が過ぎた8月下旬の暑さはどうなっているんだと言いたい。気象台は”23日の処暑、9月7日の白露、そして23日の秋分と徐々に涼しくなります”と言う。成程、気象台と君子はどう豹変しても良い様だ。
◆そして皆さんに今一つどうなっているんだと言いたいのは、この景気の悪さである。日銀も景気は指数から見て徐々に良くなっていると言っている。今度の景気回復は二極化され、生産業界から良くなっており、吾々流通業界は、不況の底に沈み放し。景気回復なんてことは幾ら背伸びしても、煙も見えず、雲も無くの状態である。いくら泣き事を言っても仕方がないので、温故知新、昔の事を勉強し直して見たいと思う。
◆ここに二百年程前に出された本がある。作者は当時のノンフィクション作家、大阪生まれのの井原西鶴先生。先生も聖人君子ではないので、身すぎ世すぎには「好色一代女」とか「好色一代男」とか一寸ぞくぞくする様なのを出しているのだが、何時の世も一緒で、世間のからくりに振り廻されている庶民が読んで面白くて為になると云う。親鸞上人のお文にも負けない様な「世間胸算用」と云う本を出している。
◆ 「サギ」「カタリ」「年の暮れのの借金取り撃退のノウハウ」「ケチ」「始末の仕方」等・・・。唯ここで西鶴は金儲けの方法は余り書いていない。昔から金儲けの方法等はあまり無かった様で、十貫で仕入れた品を八貫で売って金を回してしのいでいる様では、幾ら親から財産をもらっても早晩、家屋敷を手放さねばなるまいと云っている。
◆また一方では食うものも食わず金を貯めて、夜も寝ずに働いても、一升柄杓には一升の水しか入らない。その人の器量の店しか持てないと言う。それでは店を栄えさす主人はどうかと云うと、番頭、手代、丁稚に至るまで、手習いその他の勉強をさせ、大切に扱い、また商機には自ら敢然と勝負に出る。そしてお寺や歌舞伎(今で云うなら文化)に出資を惜しまない。と、栄える店を定義している。
◆二百年前の西鶴先生の仰せであるが、当を得ているとしか言い様がない節季に対し常々商売に油断無き様との御教訓である。
◆先日の日経には江戸末期の京都の市井学者石田梅岩と言う先生が登場している。元禄バブルのはじけた後で、やはり今と同じ状態で、八方塞がりの商人を奮い立たすのは、昔も今も同じ勤勉節約奉仕礼節等で、これは住友家創業の家訓となっている。公益を先として、浮利を追わない処に重点ある様だ。そして一様に社会への還元、文化への後見を言っている。
◆猛暑もあと暫く、三月も立てば霙が降ると呪文をとなえて下さい。涼しくなります。商売の方も同じ事で、あんまり考えると余計あついのです。
(平成9年9月5日)