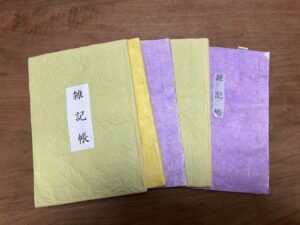時空を超えてー木々高太郎の雑記ー㉛職人芸
◆芸術の秋である。得意先廻りから帰って来た息子が「Hさん今年は伝統工芸展の出品はやめたらしいよ。あんな事に力を入れてたら、飯が食えん様になると言ってた」と伝えた。
◆以前に、毎日新聞主催の備前焼即売会に行って余り上等でないぐい吞みを、いくつか買ってきて夫々の作品についている作者の経歴書を読んでみた。そしてその作者の入選経歴を見て驚いた。大方、地方展に一、二回入選しているだけである。
◆備前焼は藤原、金重一統におさえられていると言うものの何ときびしい事か。伝統工芸展入選なんかは夢のまた夢である。然し一方でH氏の様に入選歴何回かの力のある人だから言えるのだが、あまりそんなのに付き合っていたら飯が食えないと云う人もいるのである。
◆私の友人で、中年から陶芸の世界に入った人がいる。発想が大変ユニークなので伝統工芸展は毎年の様に入選しており、今年等は三つ四つの展覧会に入選しているから大したものだ。その人が陶芸をやりかけの頃、ロクロがどうもうまくいかないので、明石の蛸壺を作る処へ見学に行った。
◆何と驚いたことにそこの主人は、蛸壺とは云へ、一時間に六十個造らないと飯が食えないと云う。要するに一分間にいや50秒に1個である。普通こういうものは土作りの時にむらなく程ないとうまく立ち上らないのだが、この人は山から取ってきた荒土をロクロ台に乗せると一気にボディから肩、口へと立ち上がってハイおしまいである。小さな石なんか手にさわったものはポイと指先ではじきとばすのである。折角来てくれたからと、糸で壺を上から下まで二つ割にして見せてくれたが、立ち上がりの左右のふくらみ、厚さが寸分違わなかった。私の友人は心に固く誓った。生涯ロクロはやらないと。彼は賢明である。
◆昔今里の方で、違棚に付ける筆返しを専門に造っている人がいた。確か当時120円位の普及品で要は安物の既製品である。材料は朴で人黒(黒丹の様な模様が書いてある)。然し私はこの筆返しの木口を見て驚いた。スパーッと切ったままである。どうにも合点がいかないので聞いてみた。建具屋の使う胴突鋸で切っただけだと言う、筆返しは木口から見ると鳩の型をしているので、カンナ等を使うと、丸身が出来たりして型がくずれるという。一刀両断と言うか木口の切れ味を見事に見せていたのを思い出す。
◆今も市井のかくれた処にこの様な名人芸を持った人がいると思う。テレビに出たりしてとうとうと芸術論を述べる理論家は願い下げである。さりげなく見事な仕事を日常茶飯事にやりとげて、夕飯の食卓で一杯のビールに人生の喜びを味わっている名人は何人もいる。
(平成9年10月5日)