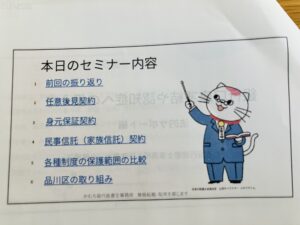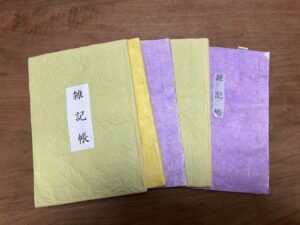時空を超えて−春男の雑記−84 寒い俳句
◆「去年今年 貫く棒の如きもの」高浜虚子が昭和二十六年の春を歌ったものである。既に七十六歳にもなった虚子は、昨日迄の去年が今日から二十六年と云う今年に変わったのだが、太い棒に貫抜かれ、押さえ込まれた様なこの戦後の不況はどうだと云っている。日本はこの年に勃発した朝鮮戦争の特需に潤うまでは失業とインフレ、労働争議に悩まされるのだが、虚子は、どうする力もない庶民の上にのしかかる太い棒を強く意識したのである。
◆一方楸邨の「鮟鱇の骨まで凍てて ぶち切らる」の句は期せずして同じ頃の作で、不細工な余り見映えのしない鮟鱇が寒い軒先に荒縄でぶら下げられていて、いる丈ぶち切られては鍋にほり込まれていると云うわけだが、この頃の国民は食べる物も着る物も無く、寒空にふるえ上がっていた。鮟鱇の様に世の中の人はボツボツぶち切られて食べられると云う図式が出来上がっていた。
◆また寒い冬の日は「木枯らしの 一日吹いて おりにけり」となる。これは江戸時代、芭蕉門下の岩田涼菟の作で、平易で誰にでも出来そうな句である。江戸の街は低い空っ風の吹く随分寒いところだった様だ。こうなると思い出すのは江戸後期の俳人、井上士朗の「足軽の かたまって行く寒さかな」で、夜の屋敷街の人通りの無い道を五、六人の足軽が無言でかたまって、急ぎ足でヒタヒタと通り過ぎて行く・・・。
◆これは寒い 厳しい世間から逃避して「冬籠り虫けらまでも穴かしこ」とシャレのめしたらどうだろう。寒い世間に愛想つかした虫けら達が、手紙で使う用語の穴かしこと左様ならを云って穴に籠ると云うのだからシャレている。
◆「冬蜂の 死にどころなく 歩きけり」村上鬼城。穴に入った虫けらさんは幸せで、なまじ丈夫で死にきれなかった蜂さんはみじめである。日だまりをヨロヨロと歩いている。冬の陽のさす、窓の硝子によく冬の蜂が止まっていて、ひょいと指でつままれる。こう云うのを詠んだのだろうか。
◆正岡子規の「いくたびか 雪の深さを たづねけり」「冬降るよ 障子の穴を みてあれば」。病気で寝込んでいた子規にとって温暖な四国で久しぶりに降った雪には異常な思い入れがあった様だ。故郷宇和島で病んだ子規は、ここで中学の教師をしていた漱石と出会うのである。
◆最後に私の好きな中村汀女の句を載せたい。
「咳の子の なぞなぞ遊び きりもなや」。一寸風邪で熱のある子供の甘えた様が、本当に微笑ましい。皆さんの小さかった頃を思い出させる句でhないでしょうか。どうぞ本年も駄文お見捨てなく、御目通し下さいます様お願いします。
(平成12年1月5日)