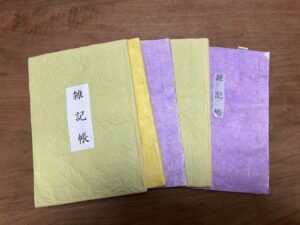認知症を知る
3/28の毎日新聞に載っていました「認知症を知る」という記事が大変興味深かったのでブログに纏めたいと思います。
https://mainichi.jp/articles/20250328/ddm/004/070/007000c
3人の方に取材した記事がありました。
①奥野修司さん…ノンフィクション作家。認知症の方を取材して著書を書かれている。
②斎藤正彦さん…東京都立松沢病院名誉院長
③恩蔵絢子さん…脳科学者 お母様が認知症になり介護された経験もある。
それぞれのお話で印象的だったところを纏めたいと思います。
① 認知症の人の内面と周囲の関わりー周囲は当事者目線を大切にー
一般的に、認知症が進行すると喜怒哀楽の表情や言葉を失うと考えられています。しかし、奥野さんが各地で20人の認知症当事者を取材した実感としては、現実は異なるそうです。認知症の方に手記を書いてもらうと、家族や周囲との関係をよく理解している様子がうかがえるといいます。また、「おこられる」という単語が頻繁に登場することから、叱られた内容自体は忘れても、負の感情は残ることが分かります。これが繰り返されることでイライラが蓄積し、暴言や家庭内での問題につながる場合があるのではないかと指摘されています。認知症の人が「孤独」や「不安」を抱えているケースはそれなりに多いと感じるとされています。
奥野さんの取材では、認知症の人が自由に将棋を指したり、歌唱したりするデイケア施設や、ゴルフの打ちっぱなしをするだけの認知症カフェがにぎわっている様子が見られたそうです。周囲の人は認知症の人に変化を求めるのではなく、彼らに合わせることが重要です。認知症の人が人生の舞台の隅にいるのではなく、主役でいられる環境を整えることが、周囲や行政、地域に求められていると述べられています。
② 認知症の診断と老化との関係ー脳機能低下 むしろ老化現象ー
2000年に介護保険制度が始まり、要介護認定に医師の診断書が必要となったことで、認知症の高齢者の受診が増え、認知症に関心を持つ医師も増加しました。その結果、病気への理解も広がりました。
認知症患者の脳を調べると、通常では見られない老人斑(アミロイドβというたんぱく質の集まり)が確認され、これを取り除くという仮説のもとでレカネマブという治療薬が開発されました。
認知症と老化現象の関係
- 65歳未満:若年発症。50歳代の認知症の人は、同世代の人が働いている中、自身は働けず、日常生活にも支障をきたすため、明らかに病気と診断されます。
- 70歳代:認知症ではなくても、一人での生活が難しくなるケースが出てきます。
- 80歳代:認知症の人と重なる部分が増えます。
- 90歳代:過半数が認知症という状況です。
医学的な概念では、認知症は「これまで持っていた能力が低下して、日常・社会生活ができなくなった状態」とされています。しかし、90歳代の人を医学的に病気と診断することに意味があるのかという議論もあります。斎藤先生は、高齢者に対して「認知症」という言葉を使うこと自体が適切なのかを強調しています。年齢を重ねれば身体機能が衰えるのと同じように、認知機能の低下も自然な現象であり、病気とみなすのではなく老化現象として受け止める方が理にかなっていると述べています。
③ ー認知症の人の残る「その人らしさ」と感情ー
認知症の人は家族を忘れ、人格が変わると言われることが多いですが、必ずしもそうとは限らないと恩蔵さんは自身の経験から語っています。恩蔵さんは、認知症のお母様を介護した経験を通じて、「その人らしさ」は何ができるかではなく、言葉を失ってもなお残る感情にあると考えるに至ったそうです。
認知症の特徴として、新しい出来事を覚えにくくなりますが、理解できないわけではなく、単に記憶として定着しにくいだけだといいます。例えば、悲しい映画を観た後、数分後にはストーリーを思い出せなくなっても、悲しい感情は残るという研究があります。つまり、出来事を理解し、感情を動かしているものの、時間が経つとその感情の理由を思い出せなくなるのです。
恩蔵さんは、多くの事例を分析することで「認知症の人にはこういう変化が表れる」という一般的な傾向を示すことは可能ですが、それでも変わらずに興味を持ち続けるものこそが「その人らしさ」ではないかと考えています。
3人のお話には、新たな気づきが多く含まれていました。
認知症基本法では、認知症の人もそうでない人も共生できる社会の実現を目指しています。そのためには、認知症の症状や感情面についてのさらなる理解が必要であると私は思います。