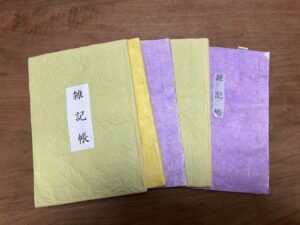時空を超えてー春男の雑記ー93 みるべき程の事はみつ
◆作九日、京都大原の寂光院が焼失した。日本経済新聞の春秋より抜粋して見ると「ほととぎす、治承寿永のおん国母、
三十にして経よます寺」。与謝野晶子が歌った寂光院の本堂が放火で焼けた。ご本尊と共に建札門院と阿波の内侍の坐像も損じた。堂内の薄暗がりの中で拝した主従の姿を思い出す。
◆壇ノ浦では、新中納言知盛は「見るべき程の事は見つ今は唯自害をせん」と言って乳母子の伊賀家永と鎧二領を着て重石として海へ飛び込むのである。この知盛の、見るべき程の事は見つと言う言葉は、平家物語の無常観を端的に言い表している。建札門院もここで阿波の内侍と一緒に海へ入るのだが、源氏方に引き上げられる。
◆都へ戻った建札門院は大原の里に隠棲して、一門の菩提を弔うのだが、一年後にここを訪れた後白河法皇に女院が
「生きながら、地獄道など六道を廻りました」と述懐すると法皇ももらい泣きするのだが、死ぬまで権謀術数をめぐらせ政治権力に執着した法皇と建札門院とは対照的である。
◆徒然草で兼好は、名誉と物欲に追い回されて閑かに暮らす事もようしないで、一生ばたばた送る程馬鹿げた事は無い。財産が多いとそれを守るのは大変な事だ。自分の健康なども構っておられないと言った調子で「金をして北斗を支ふとも」と言っている。要は死んでから、天まで届く程の金を積み上げるよりも、生きている時に飲む一樽の酒の方がずっと良い。
大きい家や立派な車、金玉の飾りも、物事をわきまえた人は、馬鹿げた事だと思うだろう。そんな物は山へでも川へでも放ってしまえと言っている。
◆また馬鹿でもちょんでもその家に生まれ合わせた人は、高い位に昇るし財産も手にする。然し聖人君子と言われる人は高い位など望まない様だ、知恵のある賢いと言われる人でも、上へ昇っていくと、それはそれで誉める人がいると思うと一方では貶す人がいるものだ。よく勉強し賢くなろう、又なったと思っている人がいるが之は一寸おかしい。教えて貰って覚えているのは知恵でもなんでもない。まして賢人ではないと言っている。なんか之は今の日本の入試制度にイチャモン付けている様だ。七十を過ぎた私に兼好は、厚生年金もあるし、食うには事欠かんだろうから好い加減にせいと言っている様だ。話は全然違うが家の建て方を述べているので原文で書いて見る。
◆「家の作りやうは夏をむねとすべし。冬はいかなる所にも住まる、夏は比わろき住居は堪え難き事なり。天井の高きは冬寒く燈暗し。造作は用なき所を作りたる見るも面白く、万の用にも立ちてよしとぞ。」夏の涼しい遊びのある家を建てなさいと言っている。
(平成12年5月20日)