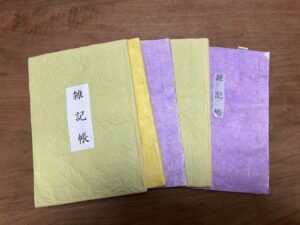時空を超えてー春男の雑記ー103 秋探し
◆神無月降りみ降らずみ 定めなき時雨ぞ冬の 初めなりける〔古今集詠み人知らず〕
なんと昨今の天気そのままの歌なので感心する。秋から冬の初めにかけてサーッと俄かにやって来る時雨の一雨一雨に秋は深まり、初冬に移って行くのは昔も今も変わらない様で、今年の滅茶苦茶暑かった夏も一雨ごとに秋から急速に冬へと移り変わりつつある今日この頃である。
◆元禄7年の十月、今では十一月の下旬に芭蕉は旅先の大坂は御堂さんの前の「はなや」の離れで亡くなるのだが、その年の夏随分暑かったと見えて「この秋はなんで年寄る雲に鳥」と言う句を残している。死の一月程前の作であるが、死の直前の体力の衰えが見事に表現されている。秋がどうしてこんなに老いを感じさすのかと言う直情を嘆き、雲に消えていく鳥と、漂泊者である自分を置き換えたのだろう。その前に芭蕉は伊勢長島の大智院に泊まっている。
そこには
伊勢の国長島
大智院に信宿ス
はせを
うきわれをさびし
がらせよ秋の寺
と言う句碑が立っている。
因みに信宿とは二泊すると言う事である。
死期を控えた芭蕉は深み行く秋と、旅に処々での弟子達との一期一会を詠み上げたのであろう。
◆今此処に近頃の若い人達には理解しにくい句がある。久保田万太郎の句
「竹馬やいろはにほへとちりぢりに」である。幼友達の事を昔から竹馬の友と言い、冬の遊びの一つに竹馬があった。小学校を六年、後二年高等小学校を終えると、殆どの男の子は丁稚奉公に出されるのである。学校を出ると再び遭うことの無い竹馬の友が、いろはにほへとの四十八文字の様にちりぢりに社会に巣立って行くのである。
◆更に一つ、昭和十二三年頃に少年雑誌の投稿短歌に出ていた
「去り行かば 何時また遭わん 夕陽さす 窓冷たきに 友ともくせり」
と言うのを未だに覚えている。余りにもその当時の私達の環境を素直に歌い上げていて忘れられない。学校を出ると仲の良い友達それぞれが、何時又遭えるだろうかと言う思いを抱きつつ別れて行ったのだ。手紙など書いた事の無い子供達、また、行く先が大阪から離れる者達にとっては、どう仕様も無く辛い事だったのだ。
◆それに比べて今は何と言う時代かと思う。携帯電話なんてのは若い人の大半は持っている。
後ろから「もしもし」と言うので、はいはいと振り返ると、なんと携帯電話であらぬ方を向いて傍若無人に大声でしゃべっている。そこには昔の日本人が感じた秋の深さ、また何時遭えるか分からない友達との別れ・・・といった情緒なんてものはこっから先も無い。若い女性が高い大きい踵の靴をはいて、大声で電話を掛けながら歩いている。
(平成12年11月5日)