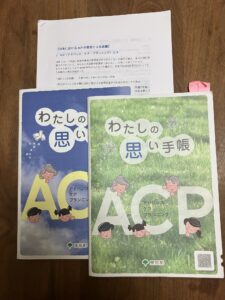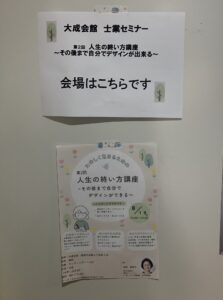時空を超えてー春男の雑記ー107 正月昔ばなし
◆昔から一年の計は元旦にありと言いまして、特に商売人は昨日の悪夢の様な大晦日が三百六十五日経つと又来るのだから用心おさおさ怠りなく、一年の計画は立てなかったら、店はつぶれますよと言う事だが、この二三年の世の中の変わり様の速さと言うものは、計画等立てていたら置いてけぼりを食い、運の良い人は独り勝ちをして他は皆沈没と言う様な事で下手な考え休むに似たりで、テレビでも見ながら寝正月が一番良い様ですが、手許にある篠田鉱造著「幕末百話」の中から浮世離れも良い所の二百年近く前のお大名家の正月風景を読んで戴きます。
◆これには秋田藩主佐竹家の江戸屋敷の正月が書かれています。二十万石を領するこの家は、源義家から明治維新迄続いた格式の高い家柄です。奥は、上は老女より下お末部屋方まで五十九名、之総て女性ですからすごいと思います。役職は老女中老、御部屋、御傍、御小姓、御次、御膳部女中、お末部屋方(歌舞伎の鏡山見たいなもの)が夫々役目分担をしています。御傍、お次の間には十人ほどいるそれはそれは美しい十七八の妙齢の女の子がおり、彼女達は、唄、三味線、踊り等がいつでも出来る様になっているのが奥の構成でありました。
◆元旦の朝、十一時頃に殿様は江戸城よりお戻りになると、すぐに表の間で御目見得以上にお熨斗盃を給わり、御祝詞を受けるのだが、実に立派な御式で、神々しい思いがしたと記しています。
◆それから大奥へ入られるのですが、お鈴の間で熨斗目振袖姿の小姓が、「お入りでございます」と告げると、鈴の口迄お見送りして来た納戸役は紫の袱紗にて捧げていたお刀を老女に引き継ぐのです。この御老女はそれはそれは屹として威厳のあるもので、殿様が奥へツト入られると次に刀を持った老女、御前様(奥様)の順に続いて行かれます。上段の間の黒塗金紙襖の前に殿様、御前様が座られ、下座に女中達が居並ぶ。そこで前に述べた美しい少女達が品の良い長唄を演じて儀式が終わると言うのであります。
◆正月二十日には将軍様は上野にある二代将軍秀忠公をお祀りしたお霊屋へ参詣する。之は今は無いのだが、日光東照宮はこれを模して造られたと言う立派な霊屋であった諸大名もこの日参詣するのだが、それらが済んだ夕方、例によって加賀様御抱え加賀鳶の梯子乗りとなる。彼等は平生捨扶持三人扶持お抱へとなっている。火事師装束各自御髪鳶口の様に結い、茶の革羽織の手鳶の研ぎ澄ました奴を一本づつ手に持ち、威勢の良い事この上なし。
◆藩のお役人はと言うと銀の兜に朱羅紗の綴れで馬上にて意気揚々と指揮をする。広小路の真中に梯子を立てると一人の鳶が猿の様にスルスルとてっぺんに登り、例の革羽織を投捨て片足を伸ばし小手をかざす。下から「見えますか」と声が掛かると「火事は火元にござい」と言う。之が十八番でこれからいろいろな芸が始まる。いずれものどかな良い正月風景であります。
(平成13年1月5日)